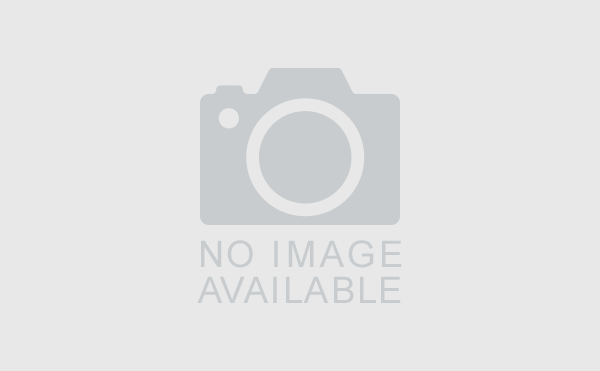まんとみだより Vol.26
とらみのめぐみ
まんとみではキミドリさんになると、千葉の外房にある付属施設、通称「とらみのはたけ」に出かけていく。今年度も小グループで8回ずつ行く事ができた。
2月末、キミドリ全員で最後の東浪見に卒園遠足にでかけた。キミドリさんにとって、もう行き慣れた場所だ。東浪見の環境を使いこなし、東浪見からさまざまなことを学び取っている。
東浪見に着くと早速、グループに分かれてお仕事をする。じゃがいもの種いもの植え付け、ブロッコリーやカリフラワーなどの野菜の収穫、かぼす、なつみかん、シークワーサー、はっさく、スイート・スプリング、キンカンなどの果実の収穫など、自分たちでどんどん動いていく。
じゃがいもの種いもを植える前に、幼稚園からそれぞれに持ってきた米ぬかを畠に撒いた。それから、種いもの切り口に灰をまぶして(腐敗防止のため)丁寧に植えた。新しいキミドリさんが6月に収穫する姿をイメージしながらのものである。


果実の収穫グループは、果実を入れた収穫かごを台車に乗せて力を合わせて、集果場所に運んだ。いくつ採れたのか、数え始めた子もいる。初めはコンテナから数えながら出していたが、シートに1列に並べると数がわかりやすいことに気づいて並べていた。しばらくすると、「107個あったぞ~!」と声が響いていた。



みんなで働いた後はお弁当。最後の東浪見にお家から持参したお弁当の他に、お料理のマルシェも開店した。さっき収穫したブロッコリーやカリフラワーの茹でたて、里芋のフライが並び、野菜はちょっと苦手という人も「あまい!」「おいしい!」と採れたての野菜の美味しさを堪能する。


本園の今年度の学校評価の重点目標に「共感力や五感をいかして 食べたい おいしいを実践する」をあげたが、まさにこの日の活動そのものだった。「おいしい」はその作物に対して、世話をし、収穫し、働いたというそれぞれの子どもたちの中に、食べるまでの「ものがたり」があってこそ、「おいしい」という真の感情が湧いてくることがよく理解できる瞬間であった。
食後は、坂滑りや「畠の神様」のお参り、水仙の花摘みなどなど思い思いに心ゆくまで楽しんだ。


ロバート・フルガムは「人生で必要な知恵は全て幼稚園の砂場で学んだ」と言っているが、まんとみの子どもたちはこの東浪見の畠で、皆で力を合わせて働くことの素晴らしさ、野菜などを育て収穫することの喜びを知り、収穫物は子どもたちを数や量への興味へと誘った。
また、みんなで食べることの喜び、嬉しさ。収穫したものをリュックで持ち帰り、幼稚園で待っているキイロさんや、オレンジさんアオさんみんなで分かち合うことの喜び。畠には人の手の及ばない自然界の大きな力が働いているということを「畠の神様」を通して感じること。
などなど、子どもたちは東浪見の環境を通して、知識でなく五感を通してさまざまなことを感じとっているのである。