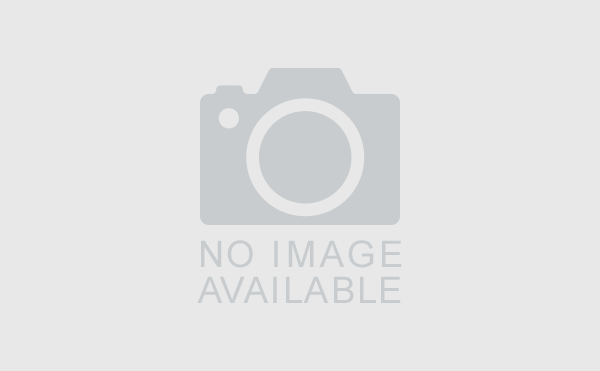まんとみだより Vol.29
かたづけるということ ~自分のしたことに責任を持つ~
日々の生活では今していることを終えたあと、それを「片づけ」て一区切りをつけ、次のことへと移っていきます。幼稚園での生活も同じです。遊び終わったら遊んだものを片づけるという営みの中に、実はたくさんの学びが詰まっています。

オレンジさん(年少さん)、キイロさん(年中さん)、キミドリさん(年長さん)たちは、それぞれの発達段階に応じて、毎日遊んだ後に片付けをしています。片づけるのも遊びの延長にあると考え、皆で取り組みます。中には片づける気持ちへ切り替えにくい時もありますが、幼稚園の生活リズムを毎日繰り返す中で、次第に『自分のしたことに責任を持つ』ということを学んでいきます。

キミドリさんになると、自分の役割意識が育ってきます。園庭や木工コーナー、製作の部屋、ホールなどを当番グループで分担し、遊んだあとのおもちゃを洗ったり、ほうきで掃いたり、雑巾がけをしたりと、園全体の掃除に取り組みます。

この掃除の時間には、大人も一緒に加わりますが、「片づけましょう」と声をかけることはありません。子どもも大人も、それぞれが自然に、静かに、淡々と自分の役割を果たしています。掃除が終わると、キミドリさん達は当番仲間で声をそろえて、「ごく、ごく、ごく、ごく、ごくろうさまでした! えいえいおー!」と言って、仕事を終えます。

そんなキミドリさんの姿を、キイロさんやオレンジさんたちは見て、憧れのまなざしで受けとめています。そして「いつか自分もああなりたい」という思いを重ね、やがて自然とその姿を引き継いでいくのです。
子どもたちが片づけを嫌がらず、むしろ一所懸命に取り組む背景には、十分に遊びきったという満足感と充実感があります。イタリアの教育学者マリア・モンテッソーリは、子どもにとって「片づけること」は大切な学びであると語っています。片付けられて整った環境は安心感を生むこと、そしてそれを子どもは好むこと、自分の行動に責任を持つこと、次に使う人のことを考えること、活動に区切りをつけて気持ちを切り替えること等など、そこでは責任感、計画性や時間感覚、他者への配慮、協調性、自立の芽生えなどさまざまなことが育まれています。「片づける」というシンプルな行為の中に、こんなにも豊かな学びがあるのです。
まんとみでは、日々子どもたちと共に生活しながらそれを大切に育んでいます。